
-
お電話でのお問い合わせ03-3433-6080 042-745-3283
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ03-3433-6080 042-745-3283

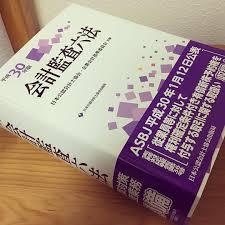
製造原価報告書と損益計算書、両者とも定められた期間の損益の状況を示す決算書となりますが、各々の関係はどのような関係なのでしょうか。また、製造原価か販管費可という点は、どのような観点で分類すればよいのでしょうか。今回は、これら両者の関係などについて、説明していきたいと思います。
Ⅰ.製造原価報告書(C/R)と損益計算書(P/L)の関係
1.基本的な考え方
発生主義→費用収益対応の原則
費用収益対応原則⇒経済的犠牲と経済的成果の因果関係に即して期間損益計算を行う。
→売上に対応する費用を期間費用とする。翌期以降の売上に対応する費用は棚卸資産として、翌期に費用を繰り延べる。
2.売上原価と損益計算書の費用表示区分
売上原価→売上を生むために直接必要とした費用の総称
製造費用→物を作るために掛かった費用で、売上原価の一部
・・・つまり、製造費用の算定した後、その内、売れた物を売上原価とする。
販管費 →販売のための費用及び一般管理のための費用。(原価以外の営業費)
営業外費用→企業の主たる営業活動以外の原因によって経常的に発生する費用。
特別損失 →企業が通常の活動以外で、特別な要因で一時的に発生した損失。
<費用の表示区分の判断順序>
原価性があるか→あれば、原価
臨時巨額か→該当すれば、特別損失
販売管理のための費用か→該当すれば、販管費。その他は営業外費用。
3.原価計算の目的(原価計算基準より)
①財務諸表作成目的
企業の様々な利害関係者に対して、過去の一定期間における損益ならびに期末における財政状態を財務諸表に表示するために必要な真実の原価を集計すること
②価格計算目的
価格計算に必要な原価情報を提供するために必要になる。
③原価管理目的
経営管理者の各階層に対して原価管理に必要な資料を提供すること。すなわち、原価低減実現のために客観的な計算を行うことによりこれを分析し、改善することをなさしめるために行う。
④予算編制目的
予算編成ならびに予算統制に必要な資料を提供すること。ここで予算とは企業の各業務分野の具体的な計画を貨幣的に表示し、これを総合編成したものをいい、予算編成過程においては、たとえば製品組み合わせの決定、部品を自製するか外注するかの決定等、個々の選択的事項に関する意思決定を含むことはいうまでもない。
⑤経営管理目的
経営の基本計画を設定するにあたり、これに必要な原価情報を提供すること。ここに基本計画とは、経済の動態的変化に適応して、経営の給付目的たる製品、経営立地、生産設備等経営構造に関する基本的事項について、経営意思を決定し、経営構造を合理的に組成することをいい、随時的に行われる決定である。
4.様々な費用等の計上区分について
(例題) ・材料仕入のためにかかった関税
・使っていない機械の減価償却費
・機械が故障した時の修理費用
・新たな製品の設計のための費用
・金型を得意先が買い取ってくれる場合の、金型費(外部購入)
・お客様へ渡したサンプルの原価
・工場の生産管理システムの減価償却費
・製品の品質上の問題があったため、手直しに要した外注費
・工員さんの家賃補助
・工場長の役員報酬
・ISOの認定費用
・製品の評価損
・材料の評価損
・工場敷地の内、賃貸している部分の固定資産税
・材料の支払を早く払ったことによる割引額
(POINT) STEP1 原価性はあるか?
STEP2 臨時巨額か?
STEP3 それは、販売管理のための費用か?
で、分類するとどの表示区分に計上すればよいか分かると思います。
5.最終表示の例題
以下の用語を並び替えて、C/R及びP/L(営業利益まで)を作成しなさい。
売上高、売上総利益、営業利益、売上原価計、当期総製造費用、外注費(原価),人件費(販管費)、販売費、経費(原価)、材料仕入、商品仕入、労務費(原価)、一般管理費、期首製品棚卸高、期首商品棚卸高、期首材料棚卸高、期首仕掛品棚卸高、期首半製品棚卸高、期末製品棚卸高、期末商品棚卸高、期末材料棚卸高、期末仕掛品棚卸高、期末半製品棚卸高
⇒以外に、上記の内容を正確に順番で並べるのは難解かもしれません。
以上