
-
お電話でのお問い合わせ03-3433-6080 042-745-3283
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ03-3433-6080 042-745-3283

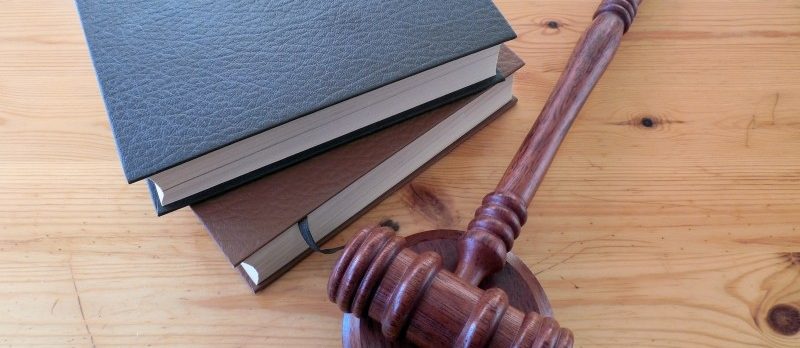
3月決算の会社においては、平成19年3月期(正しくは、平成18年9月中間決算)より、会社法が適用されることにより、様々点で大幅な改正がありました。
今回は、当時の会社法適用に伴う改正点の主要な点を改めてまとめてみました。
なお、変更点の詳細については別途記事をご用意しておりますので、そちらをご参照ください。
【商法から会社法への大改正】
会社法が新たに施行されることに伴い、計算書類が大幅に証券取引法に近づくとともに、自己株式、配当などで大幅な改正がなれました。これに伴い、会計上の表示のみならず、様々な事項に変更がなされました。ここでは、これらに関連した改正の中でも主要な開示上の改正点について、あらためて復習してみたいと思います。
【会社法における計算書類の概要】
| 会社法 | 従来の商法 | |
| 計算書類 | 貸借対照表
損益計算書 株主資本等変動計算書 個別注記表 |
貸借対照表
損益計算書 営業報告書 利益処分案又は損失処理案 |
| 連結計算書類 | 連結貸借対照表
連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書 連結注記表 |
連結貸借対照表
連結損益計算書 |
| 附属明細書 | 計算書類の附属明細書
事業報告の附属明細書 |
附属明細書 |
| 事業報告 | 事業報告 | -(従来の営業報告書が相当) |
1.適用時期
会社法は、平成17年7月26日に定められた法律であり、3月決算会社においては平成19年3月期の決算(正しくは平成18年9月中間決算)より、適用されることになりました。このため、平成19年3月期に多くの改正がされています。
2.株主資本等変動計算書の導入
会社法が施行されることに伴い、従来の剰余金計算書等(利益処分計算書、損失処理計算書等)は無くなり、株主資本等変動計算書が新設されることになりました。
当初の剰余金計算書に関しては、従来、翌期の計算結果の計画を計算書として作成していたものが、該当期の純資産の変動状況について記載するように変更されたことから、実務関係者の間でも色々苦労がありました。
ちなみにですが、従来の剰余金計算書はよく、S/Sなどと呼びましたが株主資本等変動計算書はそのような俗称の短い読み方の通説はないように感じます。皆様は、なんと呼ばれているでしょうか、私は、株変などと呼ぶこともありますが、なんとなくしっくりこないと感じています。
3.企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部に関する会計基準」及びその適用指針
会社法が施行されることに伴い、従来の資本の部は無くなり、純資産の部や株主資本と変更されました。
特に資本の部(少数株主持分等含む)が大幅に改正されています。
4.企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」
会社法が施行され、自己株式や配当に関する規定等も大幅に改正されたことに伴い、自己株式の処理や表示に関する会計基準も大幅に改正されました。
旧商法時代においては、自己株式の取得は様々な弊害がある悪と云われていたものが、この時、大きく変わりました。当時の商法学者の説は何だったのでしょうか?
5.決算短信、中間決算短信、四半期財務・業績の概況 の様式・記載要領の見直し
・注記の記載事項等に関しての大幅な見直し
会社法導入に伴い、関連当事者、税効果会計、退職給付関連、リース取引、デリバティブ取引、ストックオプション等、セグメント情報、有価証券、持分法投資損益、などの注記事項に関して、一部省略可能や記載不要などの大幅な改正がありました。
・財務指標関連の記載の見直し
⇒貸借対照表純資産の部の表示に関する会計基準の適用に伴い、大幅に記載内容等が変更されています。
・配当に係る記載の見直し
⇒従来より大幅に配当の方法等に裁量の余地が加わったことにより、配当に係る記載の方法も大幅に見直しされました。
・株主資本等変動計算書関連の記載の見直し
⇒同計算書が導入されたことに伴い、注記事項も変更とされました。
・ストックオプション等に関する注記の追加
⇒ストックオプション制度も大幅に変更があったため、これにあわせて注記も追加されました。
6.企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」
役員賞与は、発生した会計期間の費用として取り扱うと、明確化された基準です。この基準も、会社法改正に伴う改正ともいえます。
7.企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」
会社法施行に伴い、当該基準も変更になりました。内容については、大きな改正点に伴う改正がなされたといったものでした。
8.実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」
改正された会社法においては、旧商法と異なり、具体的な償却方法や償却期間の定めがなく、一般に公正妥当と認められる企業会計基準等を斟酌しなければならないとされているため、整備を行ったのが、主な改正点です。
具体的な、改正の主な事項としては、以下のとおりです。
・原則、年数を基準とする償却方法が月数を基準とした償却方法に変更
・支出の効果が期待されなくなった繰延資産は未償却残高を一時償却
9.計算書類等における監査報告書の記載について
会社法改正に伴い、会社法監査の意見区分が証券取引法監査の意見区分と一致することになりました。
端的に云えば、従来適法意見という個別意見であった監査意見が、会社法監査においても適性意見という総合意見に変更されました。
10.監査委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正
後発事象が、計算書類等に注記されることとなったことや、会社法監査の意見区分が、証券取引法監査の意見区分と一致したこと等による改正。発生時期別の後発事象の具体的な取り扱いなどについて、説明がなされています。
11.ストック・オプション等に関する会計基準
会社法の改正に伴い、ストック・オプションに関しても大幅に適用範囲等が増えたため、これにあわせて会計基準が制定されました。
なお、同基準の主な事項は以下のとおりとなります。
・ ストック・オプションを付与する取引についての注記
12.その他の改正
①金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針の改正
⇒用語の変更等
②連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針、株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針、持分法会計に関する実務指針
⇒表示の変更等
③会計監査人設置会社における会計監査人に関する事項に係る事業報告の記載例
⇒第126条の記載等