
-
お電話でのお問い合わせ03-3433-6080 042-745-3283
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ03-3433-6080 042-745-3283

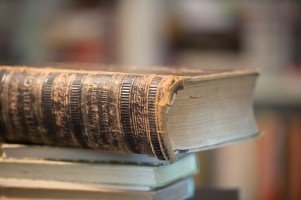
Ⅰ.基本的事項に関する監査委員会報告第66号(以下、委66号)との相違点
<基本的事項に関する比較表>
| 委66号 | 公開草案 | |
| 設定主体 | 日本公認会計士協会
→監査の視点での基準 |
企業会計基準委員会
→企業の視点での基準 |
| 基準設定時の背景 | 平成11年11月
(会計ビッグバンや金融不安等の社会的問題もあり) |
平成27年7月
(IFRSへのコンバージェンスへ向けて) |
| 基準の基本的な考え方 | 細則主義
→税効果会計が実務として定着しておらず、画一的な指針を示すことが求められた。 〇恣意性を排除するため、客観性、検証可能性を重視。 →判断要素が少ないため、硬直的となり、実質にそぐわない可能性がある。 |
原則主義 を目指したが・・・
→66号を強く意識 →細則主義的アプローチで、最終判断を原則主義的に決定。 〇実質を重視しつつ、細則主義的アプローチもあり、硬直的部分と実質的部分の両側面があり。 →実質判断部分に関しては説明責任が高くなる。 |
| 会社区分に関する基本的な考え方 | 〇結果である過去の業績等を主たる判断基準とする。
〇ストックベースのみの判断もあり。 |
〇過去の業績と将来の業績予想を総合的に判断。
〇ストックではなく、あくまで回収可能性の基礎となるフローを重視。 |
| 回収可能性に関する基本的な考え方 | 出来るだけ、恣意性を排除するため、画一性を重視。 | 企業の実態にあわせ、例外的な取扱いを認めている。 |
Ⅱ.実務上の留意点(図1 監査委員会報告第66号と公開草案の比較)
(1)分類4について
“存在する”→“生じている”に変更。
【POINT①】期末に多額の欠損金があっても、4にならない可能性あり。
また、従来は、但し書きに該当した場合、おおむね5年(つまり分類3と同様)まではあったが、分類2にもなりうる(なお、実務的には2にはなりがたい)。
(2)分類5について
従来の“債務超過の状況にある会社~中略~会社”が削除。
【POINT②】債務超過の子会社等の回収可能性の取り扱いが変わる。
(3)分類2、3について
①分類2の場合のスケジューリング不能差異の取り扱い
“一定の要件を満たす場合”→スケジューリング可能に
Ex.役員退職慰労引当金、貸倒引当金、減損(株式、土地)等
【POINT③】分類2と分類3で大きな違いがあり。
→分類2から分類3になった場合、多額の取崩しも。
②会社区分について
・業績(経常的な利益)→臨時要因を除いた課税所得に変更
→臨時的な要因(課税所得上の臨時要因も含む)を考慮できる。
・分類2→“安定的”、分類3→“大きく増減している”
なお、増減幅が大きいものの、全体として一定の高い水準で推移している場合、分類2に該当ということが明記。
【POINT④】“安定的”と“大きく増減している”の境界線は?
“安定的”とは、低位安定が認められるか?
“高い水準で推移している場合”の“高い”とは?
③分類3の場合のタックスプランニングの期間について
従来は一律5年内→“将来の合理的な見積可能期間”→5年超もありうる。
【POINT⑤】スケジューリングの達成可能性を合理的に説明が必要。
ex.経営計画が10年で作成かつ達成可能性が高い等の場合は10年が合理的。
(4)将来の課税所得の見積に関する根拠に関して
従来は、将来課税所得の基礎となる将来計画は、原則として、取締役会等の承認を得たものであることが必要であったが、今後は実質的にその合理性を説明できれば、特段、取締役会等の承認も求められていない。
【POINT⑥】第3者説明責任があることを勘案すると、外部公表している取締役会の承認がある来期計画をベースとすることが現実的。
(5)資産の含み益の実現可能性に関する取り扱い
分類2,3に該当される場合には、必ずしも取締役会等での承認は不要(従来は明記)。但し、分類4の場合には、従来同様必要となるので留意。
【POINT⑦】第3者説明責任があることを勘案すると、金額的重要性が高い見積もりの合理的な根拠としては、取締役会若しくは同等の承認の存在が現実的。
【図1 監査委員会報告第66号との比較】
| 監査委員会報告第66号 | 公開草案 | |||
| 企業の分類 | 取扱い | 企業の分類 | 取扱い | |
| 1号及び分類1 | 期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期計上している会社等 | 繰延税金資産の全額の回収可能性を認める。 | 過去(3年)及び当期のすべての事業年度において、期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得が生じている会社等 | 繰延税金資産の全額の回収可能性があるものとする。 |
| 2号及び分類2 | 業績は安定しているが、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社等 | スケジューリング不能な将来減算一時差異以外の将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性を認める。 | 過去(3年)及び当期のすべての事業年度において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が安定的に生じている等 | 一定の要件を満たす場合(※1)を除き、スケジューリング不能な将来減算一時差異以外の将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性を認める。 |
| 3号及び分類3 | 業績が不安定であり、期末における将来減算一時差異を上回るほどの課税所得がない会社等 | おおむね5年内の課税所得の見積りを限度として繰延税金資産の回収可能性を認める。 | 過去(3年)及び当期において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が大きく増減している等 | 将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年(※2))以内のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積る場合、回収可能性があるものとする。 |
| 4号及び分類4 | 重要な税務上の繰越欠損金が存在する会社等 | 翌期に課税所得の発生が確実に認められる場合、その範囲内で繰延税金資産の回収可能性を認める。(ただし書きのケース-おおむね5年内の課税所得の見積りを限度) | 過去(3年)及び当期において、重要な税務上の欠損金が生じている等(ただし、分類2又は分類3に該当する場合あり(※3)) | 翌期のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積る場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとする。 |
| 5号及び分類5 | 過去連続して重要な税務上の欠損金を計上している会社等(債務超過の状況にある会社や資本の欠損の状況が長期にわたっている会社等も含む。) | 繰延税金資産の回収可能性はない。 | 過去(3年)及び当期のすべての事業年度において、重要な税務上の欠損金が生じている等 | 原則として、繰延税金資産の回収可能性はないものとする。 |