
-
お電話でのお問い合わせ03-3433-6080 042-745-3283
- メールフォーム
お電話でのお問い合わせ03-3433-6080 042-745-3283

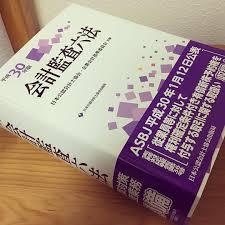
この11月16日に論文試験の合格発表がありましたね。合格された方は本当におめでとうございます。ダメだった方はまた半年頑張ってください。1回受験した後なので、効率的に知識が入っていくと思います。
当法人においては今回試験合格者を募集しておりますので、公認会計士協会のCareerNaviをぜひ御覧ください。応募をお待ちしています!
さて、論文試験に受かると「公認会計士試験合格者」という肩書きがつきます(以前は公認会計士補でした、まだ公認会計士にはなれてません)。ほとんどの人はここで監査法人に入所し、実務を経験しながら補習所というところへ通うことになります。
東京近辺であれば市ヶ谷の公認会計士会館で主に平日の18時から3時間行われます。通常は3年間この補習所に通いつつ必要な単位を取得し、考査とよばれる試験に8回?合格し、約3000~6000?文字以上の論文を何回か提出し、ときにはディスカッションの授業に出席しなければなりません。そして通常の講義は平日の18時から3時間行われます。講師によっては2時間半で終ってくれる人もいればみっちり3時間やる人もいます。ほとんどの人は仕事をしてきた後なので、真面目に聞いている人は少ないです。しかし監視が厳しく、携帯電話や居眠りは結構注意されます。内容は監査に関するものが多いですが、税金や連結会計なども含まれ、これまでの試験内容の復習がほとんどです。私の場合は市ヶ谷まで18時に到着することが難しかったので、講義はあまり参加できませんでした。2年目以降は土曜日に講義が行われだしたので、土曜に行ったりしました。考査は、日曜に行われますが、どうしても行けない日があり、そういう場合は別途15,000円払って別の日に受験することになります(考査に落ちた場合の再試験も同様です)。論文も提出期限に間に合わないと、15,000円払って下位学年のテーマを提出します。ディスカッションも自分の班の日程に出れない場合は、3,000円?ほど払って別の日程に参加します。日程に合わなかったり、考査に落ちたりするとかなりの金額を払うことになるので要注意です。大多数の人は監査法人勤務で、補習所に通うことが優先されるので2年目までに必要な単位は取得するようですが、私の場合は事業会社に勤務していたので3年間フルに使って必要単位を取得しました。監査法人とは全く違う業界で、しかも将来的にこの業界でやっていくかも不透明だったので、何度かもうやめようと思いましたが、せっかく試験も受かったのでもったいないと思い、やっとのことで補習所をクリアしました。
補習所を無事卒業すると最後の試験が待っています。この修了考査は合格率約70%と高いのですが、その試験範囲は膨大であり、また勉強する習慣がなくなっている中での試験なのでかなり苦しいです。簿記に関しては3年前の水準まで戻す必要がありますし、税務も同様です。税務に関しては、連結納税や組織再編税制、相続税まで範囲になるので、早めに対応しないととても間に合いません。これに加え、IT統制や倫理なども含まれるので(監査論は当然)、早く準備しないと大変なことになります。試験は毎年12月に行われ、私の場合は夏から勉強しましたが、連結会計や企業結合などは会計基準が3年前と変わっていたので大変でした。この試験は、最後の罰ゲームと称されるくらいですので、準備に関しては相当厳しい試験だと思います。ただし、それは周りの人も同じ状況です。働きながら勉強して、しかもモチベーションも3年前からはかなり下がっている中での試験なので、相当出来なくてもみんな受かってしまいます。一体誰ができるんだろうという難しい問題も多く、平均点は相当低いはずです。特に会計ではIFRS絡みの記述が結構求められましたが、さっぱり出来なかったことを覚えています。科目合格もないので、1回で受かっておかないと大変だと思い、結構真剣に取り組みました。合格発表まで3か月あるのですが、3か月間ずっと落ちた場合も想定しなければならず、法人税や連結の計算は続けて勉強していました。結果として無事受かっていたのでホッとしました。この試験を最後に公認会計士としての試験はなくなり、プレッシャーのかかる試験からは晴れて解放されますが、今後も実務を重ねていくうえで一生勉強は続いていきます。